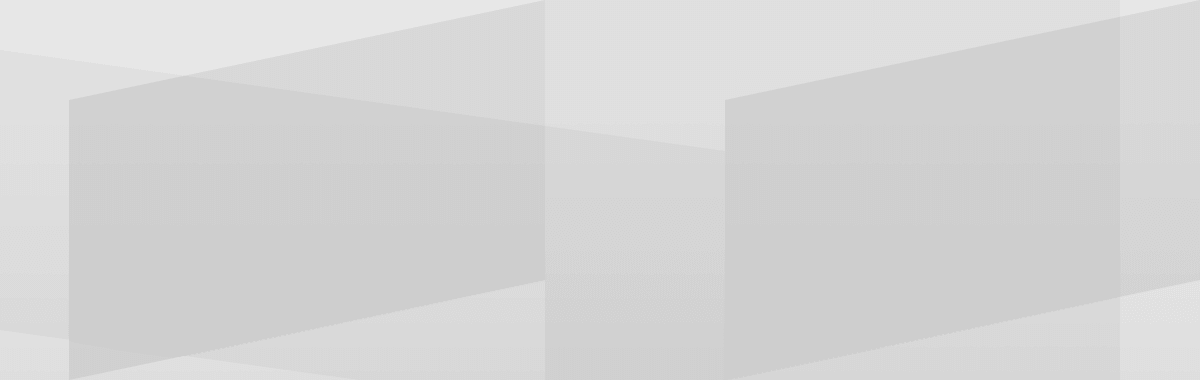
活動レポート
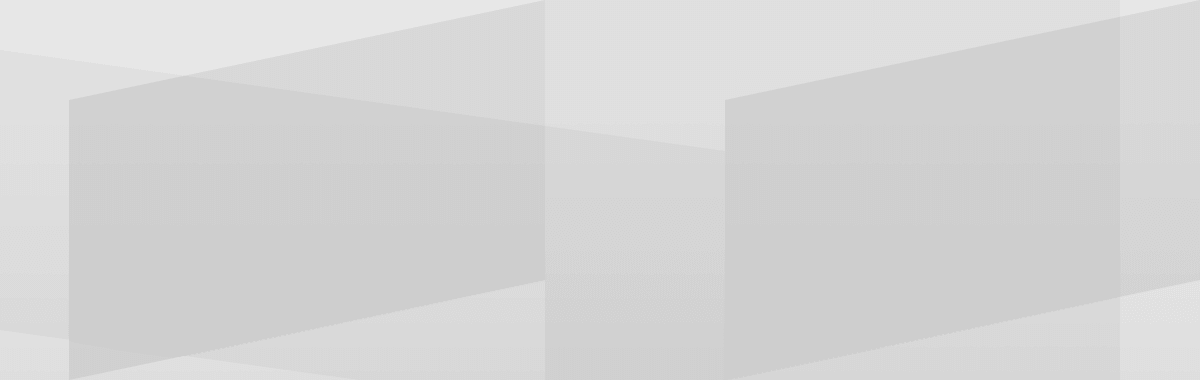

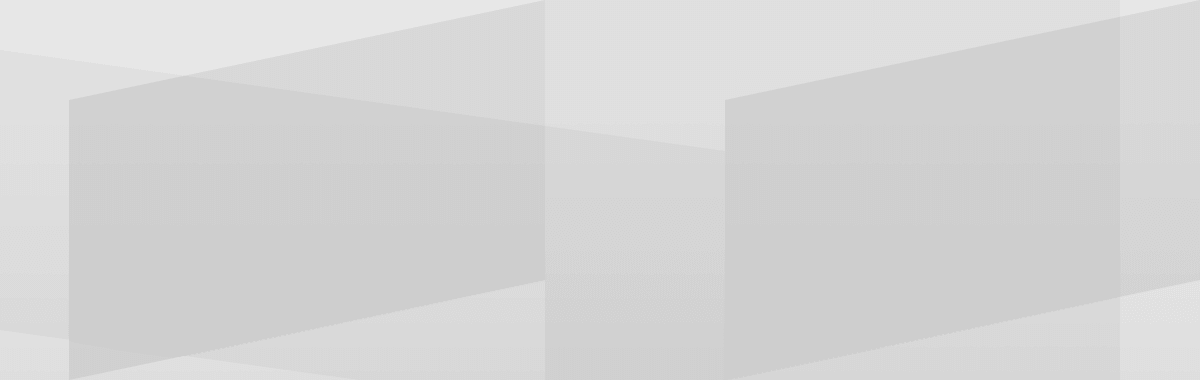
- 社会を反映する廃棄物の未来 -
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

帝京大学文学部社会学科 教授 渡辺浩平?
京都大学工学部衛生工学科卒業後、同大学大学院文学研究科にて地理学を学ぶ。その後、ケンブリッジ大学に留学。地球科学部地理学科大学院にて学び、M.Phil、Ph.D. の学位を取得。国や学部学科を移動しつつも、大学時代から現在に至るまで一貫してごみの研究を続け、現在の専門は都市廃棄物管理。EUのごみをテーマにしたフォーラムや、国連環境計画(UNEP)のワーキンググループのメンバーでもある。

近現代における科学技術と産業技術の発展は、そのまま「廃棄物=ごみ」の複雑化につながりました。電池やプラスチックをはじめ、自然界には存在しない人工素材の急増と生活変容が主因です。私が大学で学び始めた30年以上前、ごみ問題は焼却処理やリサイクル手法の発展により解決できると考えられていました。しかし実態はより複雑で、現代のごみは対処するために高度な技術が必要であることはもちろん、国の法整備、自治体の役割分担、企業の取り組み、一般生活者の行動や意識にいたるまで、幅広い領域へと課題の裾野が及んでいます。
大学時代から一貫してごみ問題に取り組んできた私が、特に研究のテーマとしているのがごみの発生段階についてです。まず、ごみの量や中身を分析します。これまでに日本、イギリス、ドイツ、デンマークなどの各都市と連携し、詳細な組成調査を行いごみの質を把握してきました。また、分析手法の開発にも注力してきました。たとえば、紙に再生原料がどれだけ使われているかを調べるために、各種の紙に含まれる紙繊維の平均使用回数を計算で推計できるようにしました。リサイクルの度合を知ることで、社会におけるごみ収集から企業の再生資源調達に至るフローの効率性が見えてきます。さらに現在では東南アジアにも研究領域を広げ、発展著しいマレーシアにフォーカスしています。東南アジアの大都市では人口も増え、経済発展も目覚ましい一方で発生するごみの増加に処理が追いついていません。行政が関与してリサイクルの仕組みを作ることも必要になってきました。ごみの種類ごとにどのような処理技術を組み合わせていくのかといった、複雑な課題に丁寧に取り組まなければなりません。動植物など自然物は自然サイクルによって分解され循環していますが、人間が生み出した廃棄物はそうはいきません。自然の浄化能力に委ねられる段階まで人間がしっかり処理することは、最低限の責任なのです。

そもそもごみとは何か。実のところ、世界は定義に今なお苦労しています。リサイクル可能なものは資源とも言えますし、貨幣価値が高くても廃棄後の環境負荷の高いものは管理が必要です。各国にごみに関する法律が存在しますが、次々と新しい素材が開発されるため、ごみの定義はすべて産業や社会生活の後追いにならざるをえないのが実情です。たとえばEUでは、EU全域でごみのルールを決めて各国が受け入れていますが、産業も文化も異なるため軋轢が生まれるケースもあります。日本も例外ではありません。当初ごみに関する要件は国が細かく決めていましたが、現在では各市町村に法律の解釈は委ねられています。収集と処理が地域ごと実施されるためです。自治体が保有するごみ処理設備の性能に応じても異なります。
しかし後追いでの対応では、廃棄されたさまざまな品物が抱える包括的な問題を正確に把握できません。そこで1990年代以降「作る側の責任」を求める声が高まり、2000年には、日本で大量生産?大量消費?大量廃棄型の社会からの脱却を念頭にした「循環型社会形成推進基本法」が施行され「拡大生産者責任」が文言として加わりました。もとより生産者の責任は、安全性や機能性の恒常的な実現にありましたが、法整備後は、製造したものが廃棄された後に生じる環境負荷に対しても一定責任を負うとされたのです。SDGsでいえば、ゴール12の「つくる責任 使う責任」という領域にも該当する内容といえます。
ごみ課題の本質は「捨てなくて済む」社会構造をどのように実現するのかに尽きます。世界の温暖化効果ガス排出のうち約30%を占めるといわれる食料を例に上げてみましょう。SDGsのゴール1、2、3にも関連する内容が記述されており世界の関心も極めて高いテーマです。たとえば、おにぎりを購入したけれども食べる機会を逃し時間が経過してしまったので廃棄すると仮定します。たった1個でも日本で生活する1億人が1年間に数回同じことをすれば量は膨大です。すると、米や具材を生産するプロセス、それを調理加工するプロセス、流通するプロセスにかかった人やモノなどの経費、労働、エネルギーなどを、全部一緒に無駄にしたことになります。では、次の購入時に1個少なく買おうと行動すれば問題は解決するかというと必ずしもそうはなりません。小売店では品切れを起こさないということを最優先で仕入れることが多いので、買われなかったものは結局売れ残りとして捨てられてしまうかもしれません。また、おにぎりを製造する工場では、小売店からの急な追加注文に応じることができるように常にいくらか過剰生産していて、何ごともなければそれは捨てられます。こういったシステム全体を俯瞰しての判断は通常なされないので、誰も廃棄された数を把握していません。したがって、お客様に販売した量が「必要量である」と判断されます。その結果「現在の供給量より多少増やしてもいい」という力学が働き生産側に伝わります。結果的に食材の生産者は農地を広げようと考え、熱帯雨林の伐採による農地確保などが生じます。CO2の吸収能力が減少し、生物多様性が失われることになる。同時に、貧困で喘いでいる人たちに食料は行き渡らず格差が広がっていくのです。

ここに挙げた例はだいぶ端折っていますが、現実はより悪化の一途にあります。食品はもとより、すべての製品にも同様のことが起こっています。廃棄することは加害者になることと同義です。重要なのは、現状を正確に理解し認識を変革していくことです。国際的な取組も必要です。たとえば、食品ロスという和製英語がありますが、これは英語のフードロスと同じ意味ではありません。国際的には食品廃棄物はフードロス(food loss)とフードウェイスト(food waste)からなります。フードロスは生産や製造段階で生じる廃棄、フードウェイストが小売、外食、家庭由来を意味しています。世界各国、産業分野ごとに取り組みは進んでいます。今一度私たちの認識を正し、行動の精度を高めることが必要不可欠で、そのためには用語の定義などを標準化しないと比較もできないし、事例の転用導入も困難です。

SDGs的視点で見れば、ごみとはあらゆる課題を凝縮した象徴的存在の一つです。同時に、SDGs的に理想とする社会とは「ごみが出ない社会」だと言ってもいいでしょう。しかし都市を中心とした人間社会が継続される以上ゼロになることはありません。社会構造、産業構造、経済構造をはじめ、生活者意識まで含めたすべてを改善していかなければ、減らすことすら難しい。「捨てない」を実現するための道筋は険しいと言わざるをえません。だからこそ、すでに普及しつつあるものの、まだまだ余地の大きい、3R(リユース、リデュース、リサイクル)は今後その重要度をどんどん増していくでしょう。そのなかで、リサイクル技術を過度に重視することには疑問です。新品からモノを作るよりマシとはいえ、リサイクルするためにはかなりのエネルギーが必要なので、大量消費して大量リサイクルするのでは環境負荷は減りません。
冒頭で語ったように、すでに状況は社会のあらゆる側面からの関与を求めています。難題は大きなチャンスでもあります。ごみの課題を解決するということは、社会における望ましい物質使用のありかたを追求するということになります。世界では今、課題解決のためにさまざまな叡智が行動を起こしています。重要なのは課題の向こうにある新しい社会のイメージと創造です。ごみの中には確かに、SDGs達成に貢献できる多くのヒントが眠っているのです。